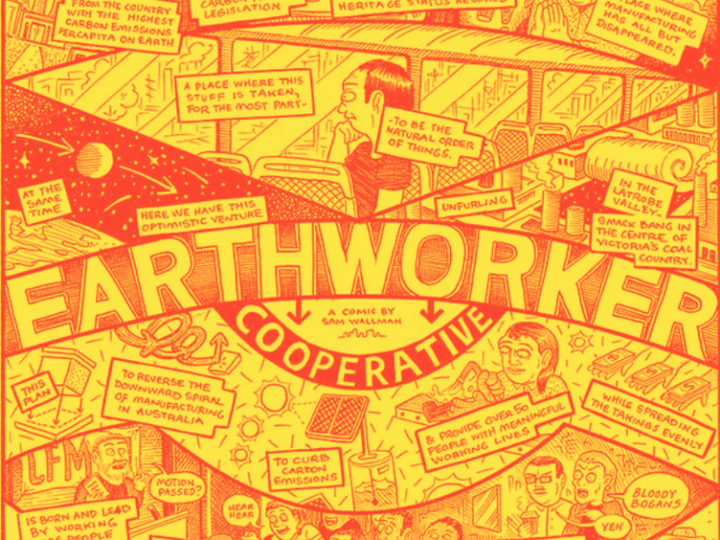戦火の列から遠ざかる日本メディア なぜウクライナからの報道を避けるのか

2月24日のロシアによるウクライナ侵攻以来、日本のメディアは他国と同様に、後れを取らないよう必死に報道している。しかし各国と違うのは、ウクライナの首都キーウ(旧キエフ)やその他主要都市から取材する日本のテレビ局や新聞社の記者が少ないことだ。日本のテレビで現地からレポートするのはフリーランス記者であり、安全な日本のスタジオから8000キロ先で起こっている戦争を分析する専門家の姿ばかりが放映されている。これに対して、AFP通信東京特派員のカリン西村記者が、官邸記者会見で岸田文雄首相に理由を尋ねた。
岸田首相は次のように回答した。「ウクライナは危険な状況であり、日本は目的の如何を問わず、同国への渡航をやめていただきたいとお願いしています。ウクライナにおいては、皆さんもよくご存知のように、いまなお激しい戦闘が各地で続いています。命の危険があります。こうした緊迫した状況でありますので、政府の取り組みについてもぜひご理解とご協力をお願いしたいというのが、この問題に対する政府からの考え方ということですので、ぜひご理解をいただきたいと思います」
このやり取りを聞いて既視感を覚えた人もいるかもしれない。米軍が2003年、イラクに侵攻した時のことだ。日本の多くの記者は取材のための渡航を控えよという政府の指示に従った。日本のテレビ局はフリーランス記者に大きく依存し、有力コメンテーターを東京のスタジオに囲い込んだ。この20年で続いて起きたミャンマーやタイ、アフガニスタンといった紛争地でも、現地に行った日本の記者は他国と比べて極端に少なかった。

ウクライナに関しては特にこの傾向が顕著だと、英インデペンデント紙のベテラン東京特派員であるパトリック・コックバーン記者はいう。ウクライナが、自称戦争ジャーナリストたちの重みで「沈みかけている」と言うのだ。一体どういうことなのか。
近年、日本の放送局や新聞社は、自社の記者をできるだけ危険から遠ざけてきた。契機となった、1991年の雲仙普賢岳の噴火では、NHKの矢内万喜男カメラマン(当時)を含む43人が犠牲になった。2003年のイラク侵攻では日本人ジャーナリストが死亡。2015年にはフリーの後藤健二記者(当時)が過激派「イスラム国」に殺害された(※Unfiltered 注1)。
2011年3月11日に東日本大震災が発災し、福島第1原発が相次いで爆発。日本の大手マスコミは政府の避難指示に従い、福島第1原発から20キロ圏での取材を規制した。20キロ圏内に入って取材を始めた記者もいたが、それはほとんどが政府からの避難解除指示が出た後のことだった。2011年4月25日、朝日新聞は震災後初めて圏内から報道したが、記事は警察庁長官の同行取材を元にした内容だった。
報道の差を埋めるのは、フリー記者やビデオニュース・ドットコムの神保哲生さんのような独立系メディアのジャーナリスト、外国通信社または日本の新聞社を退職した記者たちである。後日、戦地から報道しないことについて、ある大手マスコミの記者は、「ジャーナリストは会社員であり、社は社員を危険から守らなくてはなりません」と話した。2011年、日本テレビ報道局の当時の副編集長も同じように私に語った。「自分のような記者は、現地から報道したいと思うかもしれない・・・でもメディアという巨大企業の中では個人の自由はそうないのです。上司から危険だと言われたし、自分の判断でそこに行くことは掟破りになります。つまり会社を辞めるほかないということです」

このリスク回避の姿勢は日本の報道機関の経営層に浸透していると、元テレビ朝日記者で武蔵大学の奥村信幸教授は指摘する。雲仙普賢岳で同僚を亡くした経験のある奥村教授は、遠く離れたウクライナを報道するにあたり、日本における海外ニュースへの関心の低さをこう批判する。
「日本の報道各社は、過酷な状況の中で報道するための技術研修や機材などを真っ先に削る」
テレビ朝日は、東ティモールやミャンマーなど、危険な海外支局から奥村教授を外した。会社のこうした態度に記者やカメラマンは苛立っていた、と奥村さんは語る。
東京大学大学院の林香里教授(メディア研究)は、日本の報道機関では上司にあまり人事権がなく、だからこそ各社は銃弾が飛び交い始めるとフリー記者を雇うのだろう、と話す。林教授と奥村教授は、もう一つの理由に言語の壁と、とりわけ民間放送局における戦争報道の訓練不足を挙げる。「日本の報道各社は、ジャーナリストを雇うのではなく新卒者を総合職として採用するのです」と林教授は説明する。
大手メディア記者の例外としては、TBSの金平茂紀キャスターがいる。ジャーナリストとして、ウクライナから定期的にニュースを報じているが、金平キャスターは社員ではなく、フリーの立場に近いと、神保さん(前出)は指摘する。「会社が戦地に記者を送る場合、ジャーナリストでなく“会社員”(正社員)として派遣します。社員は社の命令には従わねばなりません。もし何か起きれば上層部が非難されるのです」
時として、特に熟練の記者からの力強い説得によって考えを改めた編集長もいるようだ。元NHKヨーロッパ総局長で、イラク戦争をヨルダンから報道した大貫康雄さんは、バグダッド出張を認めるよう上層部を説得した思い出を語る。「NHK上層部はいつも報道に気が進まない様子だったが、たまたま社長と会う機会があったのでニュースの価値を説明した」と言う。NHKを含む記者クラブ加盟社は、日本で議論されていた自衛隊のイラク派遣を取材するため、記者をイラク南部バスラに送ったが、のちに自衛隊の撤退が決まると記者団も共に帰国した。

若手ジャーナリストが日本の報道機関のサラリーマン文化に苛立っている、という内部の声もある。一方で、もちろんそれがストリンガー記者(非常勤特派員)を思いとどまらせることはなく、日本のフリー記者らは「次から次へと」ウクライナ入りしている、と北朝鮮専門家でアジアプレスの石丸次郎編集長は言う。2022年3月26日現在、アジアプレスの記者も含めて、少なくとも7人のフリー記者がウクライナに入国している、と見られる。
ニューヨーク・タイムズ紙元東京支局長のマーティン・ファクラー氏はこう語る。「結果として、訓練も組織からの支援もないフリーランサーが、世界で最も危険な場所にカメラを持って分け入っていくことを期待されている。一方で、大手メディアの記者は高額な給与を得て安定した生活を送りながら、東京で静観しているんです。日本政府の指示は危険な仕事を避けるための隠れ蓑でしかない」
ウクライナでの戦争を報じることが危険であることは否定できない。3月7日、スカイニュースのテレビ取材班が奇襲にあい、スチュアート・ラムゼイ記者が負傷した。米国人映像作家ブレント・ルノー氏とウクライナ人カメラマンがロシアの砲撃によって殺害され、デンマーク人記者2人が取材中に攻撃されたことについては、ジャーナリスト保護委員会が抗議した(※Unfiltered 注2)。
AFP通信の西村記者(前出)は、外国の分析に過度に依存すること自体、日本メディアのためにも日本のためにもならず危険だと指摘する。
「戦地に記者を送らないことが常識なのだと、政府や報道関係者の間だけではなく世間一般で考えられてしまっています。その結果、テレビは情報を発信する代わりに、現場を知らない著名なコメンテーターに意見を述べさせ、状況説明までさせています。もちろん誰にでも意見を言う自由はありますが、ウクライナの戦争は誰もがテレビでコメントできるような状況ではないはずです。はるか離れたウクライナの危険を、あたかも見てきたことのように語るべきではありません」。
(※Unfiltered 注1)ジュネーブ条約では、「武力紛争地域において職業的任務」に従事するジャーナリストを一般市民と同様、攻撃してはならないと定め、保護すべき対象としている。しかし実際、ジャーナリストが戦場で負傷したり殺害されたりすることは免れず、特に「敵」と見られる側から報道する際は、時として意図的に殺害される危険性も孕む。
(※Unfiltered 注2)国境なき記者団(RSF)は、ウクライナ紛争において4月6日時点で7名のジャーナリストが死亡し、11名が負傷した、と報告している。