頓挫する日本のパームオイル発電
「パームオイルのような燃料が生産される地域では、生物多様性が低減したり、温室効果ガスの排出、人権問題等が懸念されています」

2011年、日本は前代未聞のエネルギー危機に直面した。東日本大震災によって福島第一原子力発電所が大きな損傷を受けた後、54基の原子力発電所が安全上の理由で停止したのだ。数カ月間、日本は電力不足と停電の危険性に直面した。
政府はこれを受けて2012年、再生可能エネルギーの固定価格買取制度(FIT)を導入するとともに、分散型の再生可能エネルギーを従来の送電網に乗せようとした。大手電力会社には、再生可能エネルギー源からの電力を固定価格で買い取ることを義務づけた。これによって太陽光発電の普及率は大幅に向上。一方で、その政策には物議を醸すエネルギー源も盛り込まれていた。
これは、パームオイルを発電所で燃やして発電するというものだが、1キロワット時あたり24円(0.18米ドル)の固定料金を提供することで、事業者にインセンティブを与える政策だった。この事業は、パームオイルの価格が1キログラムあたり97円(0.80米ドル)を下回らない限り、高収益をもたらす事業になった。
その後、何年もの間、数十件ものFIT向けプロジェクトが計画された。許可を受けた発電所は2018年までに合計1,700メガワット(MW)時に達した。これは170万世帯の1年間の電力に相当する規模だった。これらすべてが実現すれば、日本の東南アジアからのパームオイル年間輸入量は、72万トンから340万トンへと5倍に膨らむ可能性がある。
「パームオイルのような燃料が生産される地域では、生物多様性の減少や温室効果ガスの排出、人権問題などが懸念されています」。大阪を拠点とする環境NPO「Hutan」(ウータン)の石崎雄一郎氏はそう指摘する。
現在、建設されているのは、5社が運営する8基のプラントのみで、約140メガワット時を発電するが、パームオイル価格の高騰によりフル稼働には至っていない。さらに大規模なプロジェクトがいくつか計画されているが、騒音や大気汚染に対する懸念から、地元の人々が反対している。
こうした反対運動は、パームオイル価格の高騰や持続可能性への要求の高まりもあり、日本のパームオイル発電利用計画を止めることができる。それにより、パームオイル生産量のトップ2であるインドネシアとマレーシアからの輸入を増やすという希望は失速するだろう。

地元の反発
パームオイルを燃やして発電するプロジェクトのうち最大級のものは、京都府舞鶴市(人口7万8,000人)にある66メガワット時の発電所だ。「舞鶴グリーンイニシアティブス合同会社」が運営し、カナダのAMPエナジー社がスポンサーとなる予定だったが、隣接する福知山市に建設されたパームオイルを燃やすバイオマス発電所ではすでに、住民から排ガスや騒音に関する苦情が寄せられ、舞鶴でも同様の問題が起きるのではないかと懸念が渦巻いていた。
2020年4月、舞鶴グリーン・イニシアティブスは解散を発表。プロジェクトが大きく後退したと考えられたが、地元の環境保護活動家や住民は勝利として捉えていた。
「舞鶴市でのパーム油発電事業からの撤退は、地域住民の熱心な行動によって成功した」と石崎は話す。「住民が家の前に反対の意を示す赤い旗を立てた。住民の団結と運動が広く知られていったことが大きな力になった」
その年の暮れ、大気汚染と騒音による損害賠償を京都府公害審査会に申し立てた後、福知山のパームオイル発電所は稼働を停止した。
現在、宮城県石巻市に注目が集まっているが、そこではジービオ社が運営するさらに大規模なプロジェクトが計画されている。環境NPOのマイティー・アースによれば、この103メガワット時の発電所では年間数十万トンのパームオイルが消費されるという。舞鶴の発電所と同様、地元では活発な反対運動が起きている。
「(計画地は)住宅地の中心に近い。騒音、悪臭、排ガス汚染が地域全体に影響を及ぼす危険性がある」と石崎は言う。「毎日33台の燃料輸送トレーラーが見通しの悪い通学路を通るため、交通事故や健康、風評的な被害による地価や住宅価格の下落が懸念される」
地元の活動家たちは、舞鶴の運動にならい、オンライン署名を立ち上げてメディアやジービオに働きかけているが、ジービオはこれには応じず計画を推進している。

環境面と財務面の持続可能性
FITスキームにパーム油を含めることは、日本の気候変動に関する公約とはますます矛盾する。日本は2020年に温室効果ガス排出量を、2030年までに25%削減(2013年比)し、2050年までにカーボンニュートラルを達成すると発表した。政府は現在、日本企業に気候変動リスクの開示を義務づけ、1550億米ドルを脱炭素化基金に投資している。また、海外投資をより気候変動に配慮したものにしようと、石炭プロジェクトへの融資を中止するなどの動きもある。
マイティ・アースの日本担当ディレクター、ロジャー・スミスからすれば、パームオイルのバイオマス由来の電力を送電網に供給し続けることで、目標を達成できなくなるということだ。
「日本は気候変動に関する目標(数値目標を含む)を達成するために再生可能エネルギーを利用したいと考えています。しかし、パームオイルを電力に利用しているのであれば、世界の排出量を、そして日本の排出量も悪化させていることになります」とスミスは言う。
パームオイルを燃焼した発電方法は、2012年にはすでに疑問視されていた。東南アジアでのオイルパーム栽培にともない、森林伐採が進み土地利用が変化することで、特に炭素を多く含む泥炭地にプランテーションが造成された場合、パームオイルが気候に大きな影響を与えることが科学的に明らかになりつつある。
国際環境NGOのFoE(フレンド・オブ・ジ・アース)ジャパンの分析によると、熱帯林を伐採した土地で栽培されたパーム油で発電すると、平均的な化石燃料発電所よりも発電量あたりの温室効果ガス排出量が多く、オイルパームが炭素を多く含む泥炭地で栽培されている場合は、その排出量がはるかに多いことがわかった。
マイティー・アースやウータンのような環境保護団体の努力は、重要な政策変更につながった。持続可能性への懸念に対処するため、今年4月からは、持続可能なパームオイルに関する円卓会議(RSPO)の認証を受けたパームオイルのみがFITスキームの対象となる。しかしそれでは不十分だ、とスミスは言う。
「RSPOは、バイオマス発電のために作られたものではありません。バイオマス発電用に設計されたものではなく、消費者製品用に設計されたものです。基準があるに越したことはありませんが、問題の核心には触れていません」
これが問題とされるかどうかさえ不明だ。2012年以降、パームオイルを巡る金融情勢は大きく変化した。
当時、1トンあたり約500米ドルだった未精製パームオイルの価格は、900ドル前後に上る。昨年の食用油価格高騰の際には、ピークで1,500ドルを超えた。この価格では、バイオマスエネルギーとしてのパームオイルは、補助金を使っても経済的にペイしない可能性がある。RSPOの要件も運用コストに拍車をかける。
結果、(日本で)計画されている1,700メガワット時のほぼすべてが足踏み状態である。プロジェクト事業者が、インドネシア持続可能パーム油(ISPO)とマレーシア持続可能パーム油(MSPO)の認証を受けたものを新しいFITの持続可能性要件として考慮するよう、日本の経産省に働きかけていることが問題視されている、と日本の環境NPOである「地球・人間環境フォーラム」の飯沼佐代子氏は言う。この2つの制度は、両国政府が支持しているが、RSPOよりも厳格ではないと広く考えられている。
「MSPOとISPOが承認されれば、事業者はビジネスがしやすくなり、これまで認証を受けていたとしても、プロジェクトを進めることができなくなるかもしれないのです」と飯沼は言う。
インドネシアは2022年9月の経済会議で、日本にISPO認証の受け入れを迫った。欧州連合(EU)がバイオ燃料へのパーム油の使用を制限していることに加え、森林破壊によって作られた商品については、環境デューデリジェンスにもとづいた輸入規制が科されるため、新たな市場を開拓するためだと思われる。
スミスは、石巻のプロジェクトや、まだ中止されていない他のプロジェクトについてもあまり希望が持てないと考えている。明らかに気候変動に悪影響を及ぼすと思われる解決策に時間と資金を費やすよりも、政府がもっと持続可能なエネルギーの選択肢に焦点を当てることを望んでいる。
「バイオマスに使われた補助金は、太陽光発電や地熱発電、洋上風力発電など、燃料を必要とせず、実際に価格が下がってきているすべての電源を助成することができたはず。パームオイルは10年前より高くなっている」
石崎は、政府が過ちに気づき、パームオイルをFITの対象から外して石巻プロジェクトに終止符を打つべきだと考えている。すでに稼働している小規模な(パームオイル燃焼発電)施設においても、補助金支給を止めるべきだと話す。
「バイオマス発電はもはやカーボンニュートラルとは認められません。森林破壊や生物多様性の損失、動植物の絶滅を防ぐためにも、FITプログラムを変更し、パームオイル燃焼発電の運用を見直すべきです」
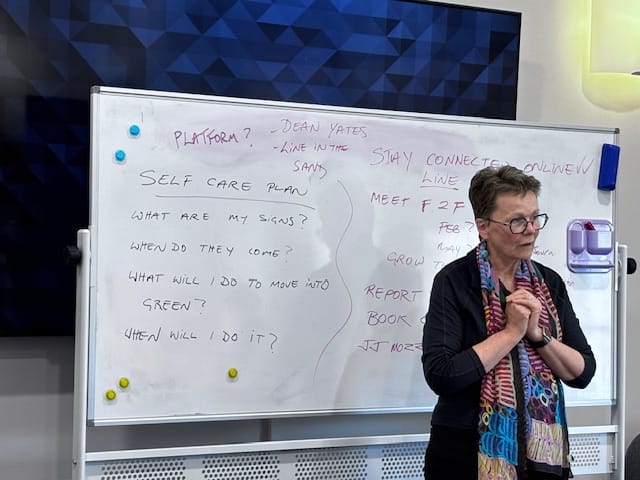


Comments ()