表現の自由の勝訴に沈黙する: 日本のメディア
真実と表現の自由を問う裁判で、ドキュメンタリー映画『主戦場:慰安婦問題論争』のミキ・デザキ監督側が勝訴した。なぜ、日本のメディアはこの話題には触れずにいるのか?

2019年6月、デザキ監督は記者が大勢集まった会見場で、自身が手がけたドキュメンタリー映画の正当性を説明した。広く注目されるようになった映画だが、5人の出演者を「(慰安婦)否定論者」と表現したことで、配給会社東風と監督が名誉毀損で訴えられていた。
出演者はそれぞれ、大日本帝国も日本軍も数千人におよぶアジア人女性の強制性奴隷化などには関わっていない、と主張した。
報道は、訴訟で1300万円の賠償金が請求されたことや今後の映画上映の禁止を求めたこと、それにより監督の職業的名誉の失墜につながったことなど詳細に触れた。2022年1月、東京地方裁判所はこうした原告らの訴えをことごとく退けたが、弁護士ドットコム以外に、この裁判が広く報じられることはなかった。
ベタ記事程度であればいくつか見られたが、判決はおおむね見過ごされた。日本のリベラル紙最大手と考えられる朝日新聞さえも報道を避けたため、監督はひどく落胆していた。
「これは表現の自由の勝利なのだから、メディアはもっと関心を示すだろうと思った」。そう話すデザキ監督は、相手の狙いは訴訟費用を負わせて制作者側を怖気づかせ、黙らせることだと指摘する。
『主戦場』は2019年、川崎市の小さな映画祭で上映が取りやめになり(抗議ののち上映撤回は覆った)、海外上映も多数企画されていたが、各国の日本領事館は会場に中止の圧力をかけた。「この映画が、司法が上映を保障したことを誇る作品ではなく、問題含みであるとしてみなさんの記憶に残ってしまうことが残念です」と監督は言う。
弁護士でテレビタレントのケント・ギルバートさん、「新しい歴史教科書をつくる会」の藤岡信勝副会長、在日特権を許さない市民の会(在特会)主要会員の山本優美子さんは、民事訴訟の原告として、『主戦場』を学生映画だと思い込み「騙されて」出演したと主張した。(デザキ監督は、上智大学の修士課程で『主戦場』を制作した。)
原告らは、映画が2018年釜山国際映画祭で封切られたことに驚き、「ナショナリスト」「歴史修正主義者」と表現されたことに憤った。ギルバートさんはこの作品を「プロパガンダ映画だ」と酷評した。
1月27日、裁判は原告側が敗訴した。柴田義明裁判長は、公開前に原告らが上映同意書に署名していたため、「制作者またはその指定する者が日本国内外において永久的に本映画を配給、上映または展示すること、公共に放送する、または複製(ビデオ・DVDなど)を販売・貸与すること」について許諾していたと判断した。また判決は、「原告らは歴史の定説などを再検討し、新たな解釈を提示しようとしている」のであって、映画で歴史修正主義者と呼称されたことで社会的評価を低下させたというのは根拠がない、とした。
藤岡さんとギルバートさんは法廷で判決を受け、不本意ながら「訴えが完全に棄却された」ことを認めつつ、「ペテン師に騙された」と主張し続けた。
監督は、どうしたら原告らは勝てると思ったのか想像がつかないという。「彼らは、ドキュメンタリーが一般公開されることはないと思って取材を受けたと言っています。私や教授だけが見る卒業制作だとしたら、なぜインタビューを承諾したのでしょうね」
裁判でより奇妙だったのは、同意書が日本語だったので何が書いてあるか分からず署名したとギルバートさんが主張したことだ。(監督側は、ギルバートさんが英語版同意書に署名したと主張した。)
「訴えられたこと自体がこちらにとって損だ」とデザキさんは言う。監督にとって、訴訟は痛手だった。疑いを晴らしたとは言え、監督と配給会社は6人分の弁護士費用を含む2年半の訴訟経費を負担しなければならない。
裁判闘争で上映計画が狂う前は、新型コロナウイルスが世界的なパンデミックになる前でもあったが、『主戦場』はハーバード大学や米カリフォルニア州バークレー大学、ドイツ・ハンブルク大学やウィーン大学など世界中で上映されていた。
デザキ監督もプロモーションのために各地を訪れ、作品への支持を呼びかけた。配給会社によると、東京・渋谷のシアター・イメージフォーラムでは9カ月の上映期間中に約7万人が鑑賞したほか(ドキュメンタリー作品としては大ヒットとされる)、韓国では60の映画館で上映されたという。日本のイルカ漁を題材にした映画『ザ・コーヴ』や愛知トリエンナーレの論争のように、酷評されたことでむしろ関心が高まったとも言える。
婉曲表現が使われたり、話題にもされなくなるような問題が増える中で(例えばNHKは、デスクや翻訳者や記者に対して、慰安婦の説明を避けるようスタイルブック上で指導し、「強要された」「売春宿」「性奴隷」「売春婦」といった表現も禁じている)、デザキ監督の作品は生々しく自主規制されていなかった。
裁判では、敵対心むき出しの取材者に対して、否定論者たちは強烈な言葉を使った。ギルバートさんは女性たちが奴隷でなく「売春婦」だったと主張。ジャーナリストの櫻井よしこさんは、日本軍が強かんなどできるわけがないと「直感的に分かる」と述べ、藤木さんはフェミニズムは醜い女たちが始動したと批判した。
著名な歴史家を挙げるよう聞かれた「慰安婦の真実」国民運動の加瀬英明代表は、「私は他の人が書いた本を読まない」と言いながら、これは米国の公民権運動による日本への影響だとし、慰安婦否定論に対する怒りが起こる韓国については、韓国人は子どもっぽくて「かわいらしい」と表現した。
この映画への半官ネガティブキャンペーンとも言える批判は、訴訟前から始まっていた。UCLAやその他イベント主催者のだれもが、イベントを企画するや日本の外交官が接近してきたと証言する。フランス・リヨンの日本領事館は、「主戦場」の上映予定だったリヨン政治学院の学長に宛てて手紙を送っていた。その内容はまるで原告の訴えのようで、「性奴隷」という用語が不適切であり、取材を受けた出演者は「ドキュメンタリー映画に使われるとも商業用だとも知らされていなかった」と映画上映に苦情を呈した。
この圧力は、日本政府の目的に沿って歴史を再編する広範な外交キャンペーンの一環である。杉山晋輔駐米外交官は赴任前の2018年、米国内各所の町に慰安婦少女像が建てられたことを受け、撤去するよう全米を回って日本政府の立場を説明すると誓った。しかしすでに3年前、米連邦最高裁は、カリフォルニア州グランデールにある少女像の撤去を求める加瀬氏や否定論者らの訴えを棄却していた。日本政府は現在、ベルリンのミッテ区における慰安婦像建立許可の無効を求めている。
日本政府は、1910年から1945年の朝鮮半島統治期に起こったあらゆる問題は解決済みであるとして、公式見解を発表している。デザキ監督の映画が重要なのは、日本の混乱した立場に着目しているからだ。
日本政府が1994年に設立した「女性のためのアジア平和国民基金」は、「慰安婦」という言葉は日本の官憲や軍の男たちに「慰安所」で性的奉仕をするよう強制された女性たちのことを意味し、そこは軍の要請で建てられたと主張する。しかし、外務省はホームページで、これまでに日本政府が見つけた資料の中に、軍や官憲によるいわゆる強制連行を示すような表現は見当たらないとして、「性奴隷」という表現も誤りだとしている。よく記事で使われる「犠牲者20万人」という数字についても「具体的裏付けがない」としている。
こうしたことを受け、デザキ監督は裁判の勝訴を、「小さいながらも真実に不可欠な勝利」だと述べる。「彼らが映画を潰そうとしていたのは明らかです。これはナショナリストが歴史をどう解釈したいかと憲法が何を保障するかのせめぎ合いなのです。つまり表現の自由をめぐる闘いです。憲法をないがしろにして歴史修正主義者を支援する政府高官が至るところにいるのは、すごく不幸なことです」
監督は、吉田清治さんの証言をもとに執筆された記事を2014年8月、朝日新聞社が取り消したことに触れ、裁判に敗訴していたら、慰安婦問題を社会的に議論することが「より困難になっていただろう」と言う(慰安婦論争自体を引き起こしたのは朝日新聞のせいだと、記事取り消しが引き合いに出されるようになった)。
「訴訟だけをとってみても、これにより慰安婦問題を議論する機会は減り、映画の価値をおとしめ黙らせようとすることで、メディアや社会に対しては危険なほどの影響が見られた。さらに残念なことに、期待したほど報道されなかったため、私たちが勝訴したことも、すべての咎を晴らしたこともだれも知らないままなのです」
デザキ監督はまだ危機を脱していない。否定論者らは、続いて刑事告発をしている。藤岡さんやギルバートさんらの代理人である荒木田修弁護士とトニー・マラーノさん、藤木俊一さんは、「判決は意味をなしていない」として、控訴する意向だ。デザキ監督の映画は今月、巡業に戻り、ペンシルヴァニア大学、サンフランシスコ州立大学などで上映される予定。何があろうと、監督を敵視する否定論者らは諦める様子を見せていない。

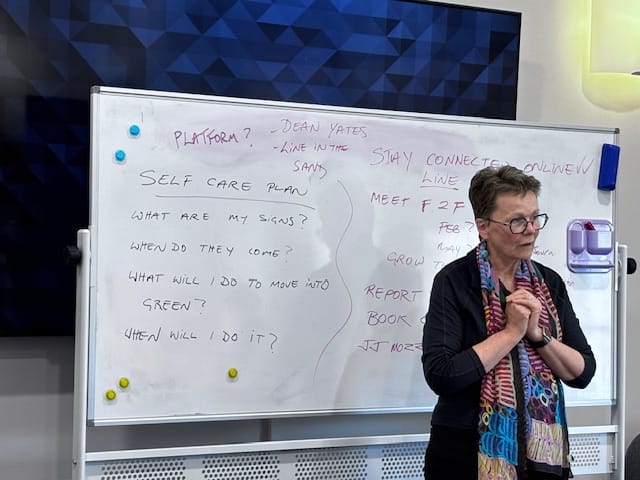
Comments ()